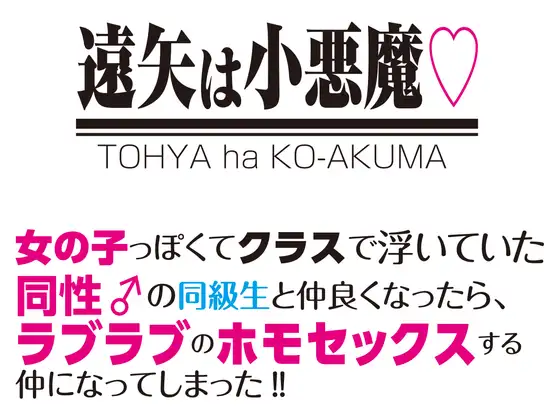![[いざなみ屋]海の記憶](https://doujin-share.com/wp-content/uploads/2024/10/RJ01268826_0.webp)
![[いざなみ屋]海の記憶](https://doujin-share.com/wp-content/uploads/2024/10/RJ01268826_1.webp)
大人になりきれない少年少女の、危うい関係
あすかは僕の憧れだった。
◇
「つかまえた」
僕は屋上の隅に追いこまれていた。あすかは僕を囲いこむように、両手で左右の手すりを掴んでいる。ほとんど、抱きしめられる距離だった。
あすかは背が高い。顔の位置は僕と変わらなかった。あすかとこれほど近づくのは初めてだった。
汗とシャンプーの匂いが、薄く漂う。セーラー服の襟元で、首筋が白い。服の中まで眼が行きそうになり、慌てて視線を外す。
あすかがじっと見ている。口元に、含むような微笑が浮かんでいた。全身が熱い。きっと、僕の気持ちは判ってしまっている。あすかはすべてを承知で、僕をおもちゃにしている。
それで、よかった。
あすかがすっと眼を閉じた。意味するところは、ひとつしかない。
まさか、ともしかして、が入り乱れ、僕は動けなかった。
決心をするにはあまりに短い時間で、あすかは眼を開いた。僕から離れ、いたずら少女のような笑顔を見せる。
「本気にした?」
◇
彩は僕の欲望だった。
◇
僕は、良くないことを考えている。
抱きしめるまでなら、彩は怒らないと思っている。
熟れた果実の香りが、ほのかに匂う。
彩を、抱きしめたい。
一歩、彩に近づく。彩は動かない。
二歩、三歩、四歩。
胸と胸がふれあうほどに近づいても、彩は道を開けようとしなかった。
両手を、彩の腰に回して引き寄せた。柔らかな太めの肉から、甘く濃い香りが立ち昇る。
彩は抵抗しなかった。肩が、大きくゆっくりと上下していた。
僕はまだ、後悔できなかった。もっと。
彩の唇が、軽く開いていた。普段通りなのかもしれない。
僕はそこへ引かれるように、ゆっくりと顔を近づけていく。彩は身じろぎもしなかった。
唇が、唇にふれた。
◇
どこかで、壊れてしまった。あすかも、彩も、僕も。
◇
「あたしをぜんぶ見たの、信明が初めてだよ」
羽根が落ちるように、あすかがふわりとマットから降りた。急いであすかに背を向け、指に力をこめて引き開ける。
ふたつの鉄の戸板は、ひとつになって重い音をたてた。開かない。鍵がかけられている。
「協力してもらったんだ。邪魔が入らないようにね」
あすかの声が、近づいていた。僕は必死に、扉を揺する。雨のグラウンドに、人の気配はなかった。
顔の両側から、白い腕がすうっと伸び、僕の肩を抱きすくめる。引き締まった身体の、わずかに柔らかな部分が、背中に押しつけられた。
「抱いて……」
◇
私は冬の雨に、下着までずぶ濡れになって、うずくまっていた。
ぱちゃりと、湿った砂を踏む音がした。
あすかさんが立っていた。もちろん、裸ではない。黒いカーディガンに黒いストッキングを履き、全身黒づくめだった。顔だけが白い。
「見てたでしょ」
しいんと頭の中が、折れそうなほどに張りつめていく。答えることもできなかった。あすかさんは切れ長の眼を細め、最高の笑顔を浮かべた。
「信明ね、あたしの中に三回も出したんだよ」
耳の奥で、ばきっと音がした。それはきっと、心が折れた音だった。
「好かん!」
私は叫んでいた。あすかさんから逃げようと立とうとするが、頭がくらみ、脚が冷たさで痺れ、壁にもたれてしまう。
「好かん! 好かん!」
両耳を押さえ、頭を振った。
突然、氷のように冷たい手が額に当てられ、顔を上げられる。あすかさんの顔が間近にあった。
「教えてあげる」
あすかさんの唇が、口をふさいだ。驚く間もなく、腐った海老のような生臭い唾液が、流しこまれてくる。あまりの臭いに、ぎゅっと眼を閉じた。
ようやく離れてくれたとき、私との間にできた唾液の糸は、妙に粘り気があった。
「これ、信明の味だよ」
◇
辛い。こんなに痛い心なんか、灰にしてしまいたい。
◇
「身体を、前に倒しなさい」
スカートからようやく顔を出した山木先生は、口の周りをよだれまみれにして、命令した。
私は机に上半身を預けた。眼の前の窓から、寂しい裏庭が見える。
スカートをまくり上げられた。山木先生の舌が這ったところが、すうすうと冷える。
尻肉を左右に開かれ、肛門が引きつれる。そこに、熱い蛭がすべりこんできた。ほじくるように、執拗にうねる。山木先生が、どうしてここまでこだわるのは判らなかった。
裏庭には御船君と亀島君、そして信明君がいた。
御船君が薄く笑って、信明君に話しかける。亀島君が泣き崩れた。信明君が、御船君の胸倉をつかんだ。
御船君が、何を信明君に告げたのか、判る。
真っ白になるほど、頭が痺れる。私は取り返しのつかないことをした。信明君に知られたことに、まだこれほど傷つく余地があった。
御船君の頭突きで、信明君が倒れた。ひどい鼻血だった。信明君は泣いていた。
胸がぎりぎりと痛い。信明君を泣かせたのは、私だ。乾いた雑巾を絞るように、涙が出そうになる。けれど、私には泣く資格もない。
そのとき、山木先生が奥まで入ってきた。御船君のときより、痛くなかった。
◇
鉄パイプを握る手に力が入る。
僕は、角を曲がった。
奥に、部屋がある。扉が開け放たれ、男の背中が見える。男は、浅黒い脚を両腕に抱えている。抱えられた肉付きのよい両足が、虚空に力なく揺れている。男の腰が荒々しく動くたび、柏手のような音がする。それに合わせて、犬の呼気が漏れる。
「出すぞ、彩」
御船の声だった。
走った。
両手で鉄パイプをつかみ、振り上げ、御船の後頭部に叩きつけた。
硬いものを砕いて、中にめり込む気味の悪い感触に、歓喜が突き抜けた。
御船の身体が、左に傾き、そのまま倒れる。
◇
僕たちは、どこへ流れ果てるのだろう。